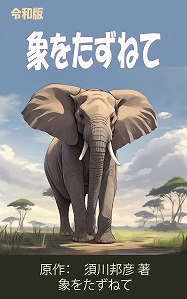 令和版:象をたずねて
令和版:象をたずねて
相武AIの著書のご紹介
「無人島に生きる十六人」と「船は生きてる」の著者である須川邦彦氏は、明治38年に東京高等商船学校を卒業し、大阪商船で一等運転士、船長などとして 遠洋航路で活躍し、日露戦争は水雷敷設隊として、第一次世界大戦は船長として参戦した海の男ですが、須川氏は航海で立ち寄った国々で象に興味を持ち、「象」を趣味にしていました。「象をたずねて」は象に関する知識と日本、アジア、アフリカでの象に関する様々なエピソードを集めた、ノンフィクション・ブックです。「令和版:象をたずねて」は、現代の読者にも読みやすく、かつ原作の魅力を損なわないように細心の注意を払って編集され、20枚の高解像度イラストを収載した読み物です。
***
原作は少年少女向けに書かれた本であり、現在の小学校中学年レベルの漢字が使われています。また、原作者の他の作品と同様の、第二次大戦前の文章表現や用語が多用されていましたが、原作の味を損なわずに現代語に近づようと注意を払いました。
地名は、原則として現在通用する表記に変更し、「中華民国」は「中華民国(台湾)」、「シャム国」は「シャム国(タイ)」などと、括弧書きの注釈をつけました。「 馬来」(マライ)は民族としてのマレー人を指す場合、地名としてはマレー半島を指す場合と元々マレー人が住んでいた地域(広くマレー半島、スマトラ、ボルネオ、及びインドネシアの諸島が含まれる)を指す場合があり、苦慮して「マレー人」「マレー半島」「マレー」などと使い分けて現代語訳しました。「ソビエト連邦」は今の「ロシア」の部分を指す場合が大半でしたが、そのまま注釈なしで「ソビエト連邦」と表記しました。
小学校で習わない漢字には積極的にフリガナを振った結果、フリガナだらけの文章になりました。元々、原作の文章表現が少年少女向けですが、大人にも、中学生(ないしは読書好きな小学校高学年)にも読みやすい本になるよう、苦心しました。
***
「令和版プロジェクト」とは、明治、大正から昭和中期までに出版された古い文体の書物を、原著の味わいを保ちつつ旧字体・旧仮名づかいを改め、現代の読者が読みやすい文体にして、豊富な挿絵の入った「令和版」として再デビューさせる。そんな発想で開始したプロジェクトです。